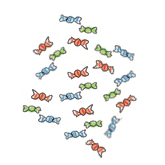「刑事さん、Trick or Treat !?」
そう言うなり、仮面の男は満面の笑みで両手を出した。黒い手袋に包まれたそれは、ものほしそうにわきわきと動いている。
「あんたね、その意味わかって言ってんの?」
刑事さん、と呼ばれた彼女はうんざりといった表情でため息をついた。職務中の格好のまま、腕を組んで彼に問い返す。
「もちろん。『お菓子をくれなきゃイタズラしちゃうぞ』だろ? 今日はハロウィンだし、問題はないんじゃないすかね」
出した手を引っこめずに、笑顔もうかべたままで、彼はさらに言葉をつけたした。
「ちなみにオレは、イタズラする気まんまんです」
ワキワキと。
十指は玄妙な動きを見せた。さすがにスリを専門にしているだけはある。
しかし、その動きにいやらしさが見え隠れするのは彼女の気のせいだろうか。
なんということもないはずの「イタズラ」という言葉も、目の前の男から発せられると、なにか違うような気がする。
けれど、そんなことを考えるより、もっと言わなくてはならないことがある。向こうが「ハロウィンだから」と主張するならばなおさらのことだ。
「それ、ハロウィンに『仮装した』『子供』が言うセリフでしょ。あんた、いつもの格好じゃない。それに日本じゃハロウィンはそんなに一般的な行事じゃないわよ。あたしだって今日は仕事だったんだから」
つきあってられない、と言う代わりに両手をあげて会話のおしまいを誘う。
そんなつれない彼女の反応に、彼は頬をふくらました。
「ノリが悪いなー、刑事さん! 確かにオレの恰好はいつものだけどさ、これは『七色いんこ』って代役専門の役者の仮装なんだから、大目に見てよ。だいたい、これが世間一般の日常着ですかい?」
「じゃあ、子供ってのはどうするのよ」
「刑事さん。男はみんな永遠の少年なんだぜ」
「うわっ、さむっ!! くさっ!! うざっ!!」
全身に立った鳥肌のせいで、口から飛び出す暴言が止められなかった。
は、といんこを見ると、その場でしゃがんで「の」の字を書いている。
「ひどいな、刑事さん。そこまで言うことはないんじゃない……?」
「あ、いや、今のはつい、ちょっとした勢いで。あはは」
「失言って、本心を表すっていうよね……。……うん……オレ、決めた……絶対……ぜえったい、イタズラしてやる。そうでなきゃ、オレの胸の痛みがおさまらない」
がばぁっと起き上がって、拳を突き上げる。
「Trick or Treat !! Trick or Treat !! Trick or Treat !!
さあ、お菓子をよこせよ刑事さん!! 日頃追われてる恨みを返してやる!! イタズラだって、性的な意味ででもしてやる!!!! R指定なんて知ったことか!」
「ちょ、ちょっと、どういうことよそれ!!」
「イタズラでも、最初は優しくするから」
「しれっとした顔で馬鹿なこと言ってんじゃないわよ!!」
「へん、嫌ならお菓子を出すんだな。もっとも、仕事帰りの刑事さんがお菓子を持ってるとは思わないけどね」
ニタリと、口の端をつりあげていんこが両手をつきだす。
最初からそのつもりだったのだろう。危ない方向にエスカレートしたのが計算かどうかは知らないが、彼女はいんこの罠にハマったのを悟った。
「くっそー! 卑怯よ、いんこ」
「さあてね、知るもんか」
ワキワキワキワキ。
黒手袋が卑猥に蠢く。
彼女は歯噛みをしながら打開策を探すが、彼の言うとおり、彼女にお菓子を持ち歩く習性はなかった。買いに行くことは、おそらく許されないだろう。いつも追跡をかわされる彼の足から、逃げきる自信はない。
……屈するしか、道は残されていないのか。
彼の両手のワキワキは止まらない。思わず彼女は襟をかきあわせた。簡単に屈するつもりなんて、これっぽちもない。瞳に強い光を秘めて彼を睨みつける。決意した彼女が感じたのは、右手の、違和感。
「……あたしの、勝ちね」
青ざめかけていた顔に、華やかに咲く笑み。
どういうことかといぶかしむ彼の眼前に、彼女は握った右手を差しだした。
花開くように開かれる五指。
そこには一つの飴玉がのっていた。
「そんな、ウソだろ」
「そういえば今日、通勤途中に『試供品です』ってもらったのよね。のど飴だけど、飴は飴。お菓子でしょ」
あげるわ、と一言を告げて飴玉をころがす。
その小さなお菓子がのったとたんに、黒手袋の十指は崩れ落ちた。
自分の予測によほど自信があったのだろう。いんこは再度しゃがみ――しかし両手は床について、がっくりとうなだれた。
「ウソだろー。ハロウィンにかこつけてやりたい放題やろうと思ってたのに。そんなのってないじゃねえかよ」
ぼそぼそと本音が漏れているが、彼女は気にしないことにした。
ハロウィンでも仕事を忘れずに試供品を配る、日本の企業の勝利である。たぶん。
彼女は先ほど彼がしたように、口の端をつりあげて話しかけた。
「ねえ、いんこ。ハロウィンなんだもの。あたしだって、『トリックオアトリート』やってもいいと思わない?」
「え?」
彼は顔をあげて、間の抜けた表情を晒す。
彼女は片手を顔の前につきだした。
「お菓子くれなきゃイタズラするわよ」
にやりと笑みながら。彼女は彼を追いつめる。
そして彼は、最大の失策を彼女に明かすことになった。
「まいったなあ。オレ、お菓子持ってないんだけど……。でも刑事さんにならイタズラされても……むしろ歓迎す……あ、いや、なにも言ってないよ?」
「じゃあ、イタズラね」
残念なことに、彼女の瞳が底光りしたのを、彼は見逃してしまった。
「目、つぶって?」
彼を立たせ、彼の両手に彼女の手をのせる。見つめあう恋人同士のような体勢に、彼は胸が躍るのを止められなかった。なんの疑念も持たずに彼女の言葉に従う。
カシャン。
聞きなれたくなんてない、いや、いっそ生涯で一度も聞きたくない金属音が彼の耳を打つ。
即ち、手錠のしまる音。
「じゃ、鍵はあたしが持ってるから」
見れば、両手に銀色の新しいアクセサリーが増えていた。無骨な作りで、両手首をつないでいる。ついでに、アクセサリーを付けた人間の自由も著しく奪ってくれる。
おそらく、多くの人間はそれを手錠と呼ぶだろう。
「じゃあねー」
立ちつくすいんこをそのままに、彼女は大股で立ち去ってゆく。
街路に靴音が高らかに響いた。
「え、ちょっと、刑事さん!? そんな、これはないんじゃない!? ってか、これ、はずれないんだけど!! ちょっと! 待ってよ、待っててば刑事さん!! うわ、ホントに置いてく気だよこの人! ねえ、刑事さんてばっ!!!!」
遠くなりつつある彼女の背を追って、走りだすいんこ。
しかし、両の手を自由に使えないせいで、普段の速度には到底届かない。
彼女はふりかえり、彼のおかしな姿を確認して、駆けだした。
いつもと違う、追われる立場に、こみあげる笑いをこらえながら。
了