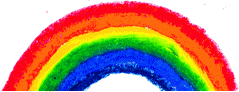スモッグがかかったような灰色の空。日本とは違う匂いを含んだ異郷のビル風。
千里万里子はアメリカに来ていた。個人的な休暇を使ったものだが、自発的なものではない。長いつきあいのある青年に、どうしてもと頼まれたのだった。
彼が万里子を連れて行ったのは、自由の女神像でもなく、ハリウッドでもない。どちらかといえばスラムに近い、さびれた街の無縁墓地――彼の恩師の墓だった。
名を、トマス・ウィリアムズ。七色いんこを育てた天才役者だ、と青年は語った。七色いんこという名をつけたのも彼だという。
七色いんこ。
万里子が長い間追っていた泥棒役者の名前だ。彼の名が演劇界から消えて久しい。最後の大舞台を踏んだあと、代役専門の泥棒役者はぱたりと姿を消した。
それと入れ代わるように、一人の有望な新人が現れた。経歴は一切不明。どんな劇団に所属し、どんな教えを受けていたのか。幾度問われても、彼は何も語らなかった。ミステリアスな新人は、舞台から降りるとたちまち寡黙な青年に変わってしまう。それは想いを確かめあった異性の前でも同じで、時折万里子は物足りなくなる。
目の前に眠る人に関しても、以上のことぐらいしか聞かされていなかった。
「あの、さ」
花束を置いて静かに手を合わせる彼の背に言葉をかける。青年は瞳を開いて、なに? と首をかしげた。
「……なんでもない」
寂しげな彼の微笑みを見ると、何も言えなくなってしまった。彼の沈黙はどんな言葉よりも雄弁で、死者への沈痛な祈りを感じとれた。
かすかに風が吹きぬける。花束を包んだセロファンが揺れて、ガサガサ音をたてた。
「僕はさ」
ぽつり、と青年が言葉をこぼす。視線は十字架に据えられたままだった。
「あなたに出会って、多くのことを学んだよね。演技はもちろんだけど、人とのつきあいとか、世間の常識とか、色んなことをさ。そのたび世界は広がって、僕は嬉しくて仕方なかった」
口の端が、少しだけほころんだ。生前を思い出しているのだろうか。瞳に浮かぶ光は穏やかなものだった。
「でも……いや、だからなのかな。僕はいつか、あなたに返したいと思ったんだ。日本のことや、ずっと言わなかった僕のことや、僕の大好きな人のこととか。けどトミーは、聞く前にそちらに行ってしまったね」
彼は空を見上げ、一呼吸おいた。そんな些細な仕草も絵になるのは、彼が一流の役者だからか、それとも万里子が彼に惚れているからだろうか。
「墓前に報告なんて、七色いんこのキャラじゃないけど、僕は、僕だから。許してね、トミー」
ようやく彼の顔に、本当の笑みが浮かぶ。青年は立ち上がり、確かな足取りで万里子の隣に並んだ。
「紹介するよ、トミー。彼女が、僕の大切な人」
すっと肩を抱かれ、体を寄せられる。
「もう、二度と離さない。ずっと守りぬくって決めたよ。トミーの時のように、悲しい思いはしたくないから」
耳もとで、囁くように彼は告げる。故人に向けたもののはずなのに、自分に向かって言われているようでもあるようで、万里子はハッと顔をあげた。
かちあった視線の先には、青年の真剣な瞳。
「万里子」
優しい声が鼓膜を揺らす。
「君に、色々な話をしたいんだ。トミーが僕にしてくれたように、或いは、まだ幼かったあの頃のように。……とても長い話になると思う。語り終える頃には、僕たちはおじいさんとおばあさんになってるかもしれない。それまでずっと、話をしたい。側に、隣に、居てほしい。とてもワガママなお願いだとはわかっているけど、聞いてくれないかな」
それはとても遠回しなプロポーズで、舞台で紡がれるようなきらびやかなセリフとは似ても似つかないものだった。それでも、彼が紡ぐ真実は、今の言葉にしかないだろう。
気恥ずかしさに、万里子は顔を青年の肩にうずめ――そして、ぼそりと呟いた。
「あたしは、人の話を聞くのなんて苦手だから、つまんない話なんかしたら、承知しないわよ」
青年の顔にパッと笑顔が咲く。
それでは手始めに、本日のお昼ご飯の話でもいたしましょうか? おどけて言う彼に、万里子はうまい文句を返せない。ごもごもと口ごもると、青年の笑みはさらに深くなった。なんてひどいやつ!
若い二人を見守るように、トマス・ウィリアムズの墓は静かに佇んでいた。
了