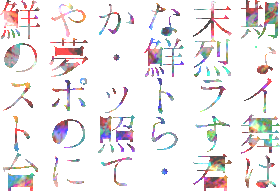■注意
■死ネタ
視線を上にあげれば、神の罰であるかのように強烈な光が降りそそいでいる。母子姦通という大罪を犯した古き王は自ら両目を潰したそうだが、ならば俺の目はこの光が潰すのだろう。現に視界は白くかすみかすみゆき、前方数メートルにある客席だってよく見えない。もちろん、スポットライトが偽りの太陽と化している舞台では、客の顔が見えないなんてことはあたりまえのことだが、そうではない。いつもなら輪郭ぐらいならわかるものだが、今はアクシデントに眉をひそめる観客たちの囁きがうねり、どよめきの海になっていくのを聴覚が捉えているのを知るだけだ。
あーあ、やっちまったな七色いんこ、と、俺は俺に話しかける。観客の不安ももっともだろう。一人舞台のさなか、突然の銃声。それにあわせるかのように役者は倒れ、なんと巧みな演出のたまものか、役者のまわりから赤い液体がにじみだいしていく。役者はなかなか起きあがらない。まるで先ほどの銃声が本物であったかのように。鼻の効く者なら、かすかにただよう花火のようなにおい、すなわち火薬のにおいをかいで、顔色をなくすかもしれない。果たして観客全員が悟るのはいつのことになるだろう。目の前の役者は死にかけているのだと。
舞台は幕が下りるまでが舞台。人一人が死にかけているっていうのに、観客がパニックに陥らないのは、この七色いんこの天才的演技のたまものと言える。俺がいま演じているのは「銃で撃たれた死体」だ。脳をジャックする痛みと体が冷えてゆく失血感に耐え、俺はぴくりとも身動きしない。もし「本当に」銃で撃たれたのなら、役者はきっと激痛に呻いたり、体を痙攣させてりなんかして、観客に「本当」を露呈させてしまうだろう。そう思っているからこそ、観客は動かない。これで観客を騙し通せればおれの勝ち。たといこの命の火が消えてしまっても、構いやしない。トミー、もうすぐそちらに行けると思う。
劇の進行に特に問題はなかったから、幕が下りるまではあと5分程度だろう。録音しておいたナレーションとBGMがそれを伝えている。それから舞台袖のスタッフが異変に気づくのにどれくらいかかるだろうか。それとももう気づいてしまっているだろうか。どんなことが起こっても、絶対に予定以外で幕を下ろすなと厳命しているから、舞台を壊してしまうことはないだろうけど。ああ、それにしても舐めていた。痛い痛い痛い痛い。息をするたび胸を焼かれるみたいだ。アメリカ時代、何回か撃たれたことはあったから今回もなんとかなるだろうと思っていたけれど、まさか腹と胸に二発とは。相手もプロということだろうか。でもプロなら頭をやったほうが確実だと思うけどな、こんなふうに痛みを感じる時間なんて残さずに確実に始末を。でも舞台で脳漿なんてぶちまけたら、銃声が「本物」だとばれてしまうから、この配慮は逆にありがたいのかもしれない。ああでも、血がここまで広がるとは予想外だったな。後片付けが難儀そうだ。だくだくと流れていく血を吸いきれずに、衣装が赤にじっとりと染まり、舞台の上に血だまりが領地を拡大してゆく。それに比例して激しくなる呼吸を必死で抑える。激しくなるよりか、絶え絶えになってくれたほうがごまかしやすいのに。熱い痛みから少しでも逃れようと、俺はどーでもいいことばかり考える。スポットライトが眩しい。横に倒れているけども、角度がついているものだから、光がまっすぐに眼球に飛びこんでくる。普段からマスクをつけている身には大変つらい拷問だ。本当に潰れてしまうかもなあ、なんて暢気なことを思う。
「なにやってんのよあんたたち!」
鋭く甲高い声が突き刺さる。鼓膜ではなくて、穴が開いた胸に刺さったのかと思った。もう二度と聞かれないと思っていたのだ。七色いんこ――いや、鍬潟陽介が最も愛する人の声。どうやら彼女は舞台袖でスタッフたちを怒鳴りつけているらしい。おいおい、舞台袖でおしゃべりはは厳禁、ましてどなり声なんてもってのほかだぜ刑事さん。やめてくれよ、これが観客に本当のアクシデントだってばれたらどうしてくれるんだい? え、なに? 幕を下ろせ? あいかわらずひどいなあ刑事さんは。これが俺の一世一代の舞台だって知ってるくせに、なんでそんなぶち壊しにしちまうようなこと言うんだか。だけどそりゃダメだぜ。スタッフにだってプライドがある。勝手に入ってきた女刑事なんかの命令は聞かないだろう。そんな国家権力の横暴は許されない。残念だったね、なんて俺は完全に人ごとのように刑事さんのどなり声を聞いている。末期の最期に聞く声が最愛の人の声なんて、俺はわりと幸せな男なのかもしれない。どったんばったん暴れているのは、刑事さんが暴れてる音だろうか。あのじゃじゃ馬娘を取り押さえるのは大変だろう。スタッフ諸君の健闘を祈る。
「いんこ!」
じりじりと長い時間が過ぎて、ようやく幕が下り始める。
舞台袖から叫ぶけれど、こちらに来ないのはスタッフに取り押さえられているからだろう。完全に幕が下りるまで、舞台は完全に虚構でなくてはならない。たとえ誰であろうとも、侵してはならない領域がある。彼女もそれをわかってくれるだろうか。それを守るために、俺が命をかけたことを、許してくれるだろうか。おそろしいほど遅く下りてゆく幕は、俺のすべてを終わらせるだろう。父への憎悪も、彼女へ愛も、俺自身の人生も。幕が下りる。幕が下りる。観客の拍手の雨の中、ゆっくりと幕は落ち、とうとう裾が舞台に接吻する。それがスタートの合図のように、彼女が駆けてくる。俺はそれを、霞んだ瞳で見ていた。もう、演技は必要ない。俺の勝ち。彼女を迎えようと身を起こそうとした時、さらに強烈な光が目を灼いた。角度が悪かったのだ。強烈な光。霞むのではなく、白く閉ざされる視界。罪には罰を。彼女の思いを無視して身勝手なふるまいをした男には、重い罰が必要だ。くらむくらむ目。熱く焼ける胸。冷える指先。きっとこの身の火は消えた。せめて、せめて君がここにたどり着くまでは、生きていたいと思ったのだけど。
君の叫び声も、もう、聞こえなかった。
了