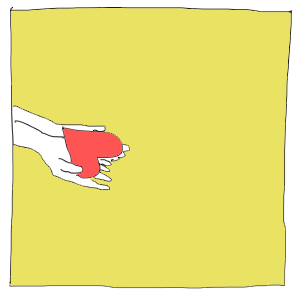■希望ヶ峰時代
■大和田くんは自宅からの登校。
■大和田くんがすこしおセンチで、ややブラコン気味。
優しくされると後ろめたくなるのは、石丸にアニキのまぼろしを見ているからだ。
石丸は風紀委員で、ルールに厳しくて、免許をとったら制限速度以上を出しそうにないやつで、アニキとは似ても似つかない。石丸はアニキじゃない。石丸はアニキじゃないとわかっている。わかっているのに、石丸の隣にいると、アニキの横にいるのと同じくらい安心して息が吸えた。
試験前なのだ、よりいっそう勉強をしなければ、と眉をつりあげる石丸に、じゃあオレんち来て勉強しねぇか、と誘ったのはアニキと勉強なんてしたことがなかったからだ。石丸は誘われるがいなや、散歩のリールを見せられた犬のようにパアッと顔を輝かせた。君の口から、勉強の二文字が聞けるなんて、と大げさに男泣きまでしやがる。アニキだったら、熱でもだしたのかと笑いながらひたいに手を当ててくるだろう。だから、石丸はアニキじゃない。
親が帰ってこない家は、ほとんど一人暮らしみたいなもんだった。ぼろ家ですまねぇなと詫びながら、ちゃぶ台をだして茶をいれる。石丸はいつも通り、背筋をまっすぐそらして、正座をしていた。客用どころか自分たちが使う座布団すらないから、畳にじかに座らせることになったが、気にしている様子もない。まったくふつりあいだろう。クソみたいな家のなかに花を一輪を活けたようで、石丸のまわりだけ、空気が澄んでいるような気がした。
誘ったはいいが、動機が不純なものだから、真面目にお勉強いたしましょう、なんて気にはならはずもない。石丸は黙々と鉛筆を走らせて、時々「む?」とか「ああ」とか喉の奥で唸っている。怒られないように白いノートを広げてみたはいいいが、紙面はいっこうに埋まらない。かといって、黒い文字がうじゃうじゃ並んでいる教科書を読む気にもならない。ページをめくったり、「問題1」なんて文字をことさら丁寧に書いてみたり、紙のはしをいじくっていると、石丸が顔をあげた。
「君、まったく集中していないな?」
はじめっから言い訳もきかずに、決めつけて話すやりかたも、アニキはしなかった。うっすらといらだちを宿した赤い目をまっすぐに見られずに、寒くってよぉ、と愚にもつかない言い訳をしてみる。石丸はひとつため息をついて、けれども責めるようなことを言いださなかった。
「今日は、君の自発的な勉学へのとりくみを評価したいからな。最初から完璧なんて求めていないさ。気温が気になるなら、暖房を入れようか。ストーブはどこだね? 見当たらないが」
「いや、オレんちはストーブ出す前に、こたつ出すんだわ」
それは情緒的だなと鉛筆を置いた石丸に座っているよう告げて、こたつを持ってくる。押入れにつっこんだこたつを出すのは難しいことじゃないが、面倒くさくていつもアニキと揉めていた。石丸とは、こんなことでケンカしない。だから、石丸はアニキとは関係ない。
こたつ布団は湿気ったせんべいいたいみたいにしおれていたが、問題ないだろう。ほこりで死ぬやつがいるわきゃねぇ。石丸はちゃぶ台を隅によせて待っていてくれた。わりぃ、とひと声かけて布団を手渡す。こたつ机を部屋のまんなかに置いて、コンセントを探していると、石丸が硬い声を出した。
「こんなことを聞くのは失礼なんだが……これ、前に洗ったのはいつだね?」
「……覚えてねぇな」
石丸の口のはしっこが、ひくひくひくっ、と三回跳ねた。
「まさかとは思うが、このまま使う気かね?」
「なんか問題あっかよ」
「大アリだ!! ほこりはくっつしているし、ところどころシミがにじんでいるし、なんだかカビくさいぞ! こんなこたつを使っていては、君の健康を害するっ!」
「じゃ、どうしろってんだ」
「決まってるじゃないか。洗うんだ!」
思いこんだら一直線。イノシシみたいな石丸に、風呂に案内させられて、ついでに洗剤のありかも白状させられた。クソ寒いってのに、勢いよく蛇口をひねって、湯になるのも待たずに風呂桶に栓をする。さらさらと粉洗剤を投入したかと思えば、じゃっぽーん、と、止める暇もなくこたつ布団を風呂桶に投げ入れる。あれよあれよというあいだに、びしょぬれ布団のいっちょあがりだ。
隣で唖然としている空気を読まずに、石丸はキビキビとズボンとシャツの裾をまくりあげる。断りひとつ入れずに風呂桶に入って、布団を足で踏みつけた。
「さあ! 君も手伝いたまえ!」
ぺかーっと光る笑顔に、思わず、おう、と答えてしまう。が、裾をまくるためしゃがむことすらできずに、ぽかんと石丸を見ていた。布団のうえで足踏みをするたび、じゃぼじゃぼと水が揺れて、透明だったのが濁っていく。ぶくぶく白い泡が生まれるが、それもすぐに茶色く濁る。泥水のようになったのを見ると、少し栓を抜いて、水を入れかえた。石丸は慣れているのか、やけに手際がいい。クリーニングってガラじゃねぇもんな、とひとり妙なところで腑に落ちた。水が湯に変わりはじめたのか、ほのかに湯気がでてくる。
「すごい汚れだぞ。毎年使っていたのかね?」
「そういや、ガキのころからずっと使ってんな」
「まさか、その頃からずっと洗ってないってわけじゃないだろうな……」
「さてなぁ」
風呂桶のなかで棒立ちになった石丸を手伝うべく、両手両足をむき出しにする。狭い風呂、しかも風呂桶のなかとなると、体がぶつかり合うのは当然のことで、いつのまにか布団を洗うよりも、押しくらまんじゅうでもするように、はしゃぎながら互いの体をぎゅうぎゅう押しつけあっていた。
すすぎも脱水も、石丸の言うがままに布団を踏んで、物干しに吊るすと、腰に手を当てた風紀委員は満足そうにうなずいた。最初のテスト勉強を忘れてくれていりゃ万々歳なんだが、そうはいかないのが超高校級。ずいぶんと脱線してしまったが、勉強に戻るぞ! と、石丸は号令をかける。寒ぃのは解決してねぇんだけど、と口をとがらせてみたら、無造作に両手をつかまれた。
「君は時々、子供みたいになるな」
苦笑いをしながら、石丸だって冷たいままの手で、少しでも熱を生みだそうとして肌をこする。男のすることだから、動作自体はガサツで荒っぽいのに、石丸の優しさが染みていくようだった。ぽろっと、こぼれてしまう。
「うっせぇ。オメーがアニキみてえんじゃねぇのかよ」
「そんなつもりはなかったが……」
「いや、そうじゃ、ねぇ! 気にすんな! 違ぇんだ!」
失言であることは自分にしかわからなかったが、石丸の手が止まった。冷たくこわばったままの手が、枷のようだと思う。
「なにが違うのかわからないが、おかしなことではないと思うぞ。だって僕らは、兄弟じゃないか」
「それと、これとは話が違ぇって……」
「違わないな。僕は君の兄弟だ。時として僕は君の兄になり、君は僕の弟になる。そして時に僕は君の弟になり、君は僕の兄になる。兄弟って、そういうことだろう?」
まっこうから見つめる赤い両目も、ぎゅっと包みこむ手も、やっぱりアニキと違う。石丸清多夏が大和田大亜でないのは、当たり前の話で、どうやったって石丸はアニキになれない。石丸にアニキを求めるのはお門違いだ。
だけど、こいつはオレの兄弟だ。
「そう、だな……」
畳の目もほつれた古臭い部屋のなかで、日にあたりながらうなずいた。石丸がまた、ゆっくり手をこすりはじめる。ガサツだけども優しいそれに、もう後ろめたさを感じることはなかった。
了